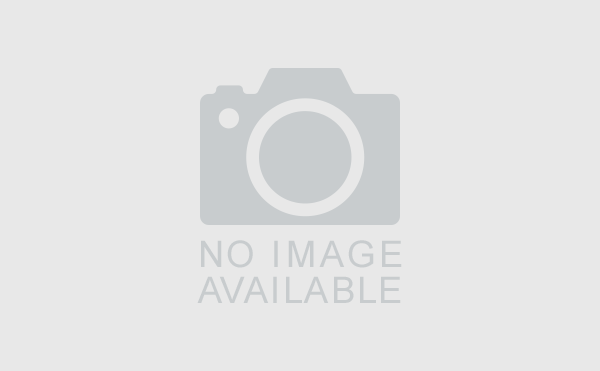離断性骨軟骨炎
関節の中に軟骨(なんこつ)が剥がれ落ちてしまう障害で、膝関節・肘関節に多く発症し、足関節や股関節にも発症することがあります。特に成長期の小中学生(性別では約2:1で男性に多く10歳代が好発年齢)に多く発症します。
膝関節では大腿骨の内側が85%、外側が15%の頻度で、まれに膝蓋骨にも起こります。
肘関節では、外側の野球肘とも言われ投球によるストレスが主な原因と考えられています。初期には症状が軽いことがあり、練習を続けていると知らない間に症状が進行してしまう事があります。症状が進行すると痛み以外にも、肘の曲げ伸ばしがスムーズにいかなくなったり、剥がれた軟骨(関節ネズミ)が骨の間に挟まり肘が動かなくなったりもします。
足関節の症状はその進行の度合いよって大きく異なります。発生初期は足首に軽い違和感がある程度で、痛みもほとんど無く生活することが可能です。
しかし症状が進むと、一過性の足首の腫れ(運動を休止すると腫れは消失することが多い)や体重をかけると足首の奥が痛む(深部痛)ようになり、足首を完全に伸ばしたり曲げることが出来なくなります。
離断性骨軟骨炎は、初期(透亮期)・進行期(分離期)・終末期(遊離期)と3つに分けられますが、
下肢での症状が強い場合は、杖を用いて免荷とし、症状が軽快してくれば徐々に荷重をかけてもらいます。
スポーツ活動への復帰は徐々に進めていきますが、以前の競技レベルまで回復するには数カ月~1年くらい要します。
一方、保存療法で痛みの改善が得られない場合には手術となります。
当院では、問診、触診、各種徒手検査をし、検査が必要と判断した際は、まずは提携させていただいている整形外科でレントゲンやMRI検査を行っていただき、診断してもらいます。定期的に診察、MRI撮影をしながら整形外科医師と連携して治療を行っていきます。
治療は患部の痛みや腫れを取るための物理療法(インディバアクティブセラピー・超音波)や、患部の周りの筋トレを行います。例えば膝ですと、運動不可の期間が半年ほどかかることもあります。
その際は、復帰したときにより良い状態にする為に、体幹トレーニングや足趾をしっかり使えるようにエクササイズ指導をしていきます。