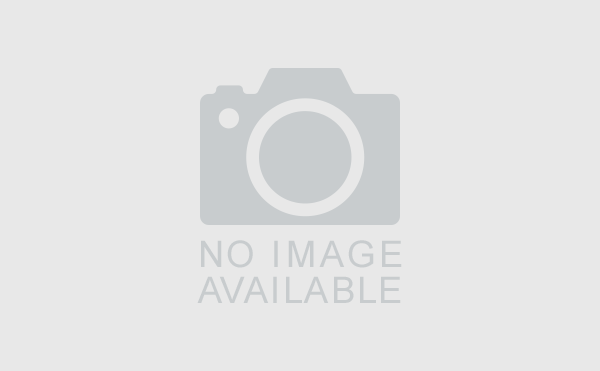加藤 久選手インタビュー

久保田総院長)今日はお忙しいところお越しいただきありがとうございます。くぼたスポーツ接骨院の患者様にはサッカーをされている方がとても多いので、先生の現役時代のポジションやプレースタイルについてお話しいただけますでしょうか?
加藤先生)どこまでさかのぼるかですが、小さい頃は前の方、つまりフォワードをやっていました。高校1、2年生ぐらいまではフォワードを続け、その後は中盤とフォワードを兼ねてプレーしていました。大学に進学してからは中盤、2年生になってからはサイドバックをするようになり、その後はセンターバックを任されるようになりました。現役の最後まで、基本的にはセンターバックを務めていました。
久保田)代表チームに呼ばれた時はいかがでしたか?
加藤先生)代表チームに呼ばれた時、大学では中盤でプレーしており、大学のリーグや試合ではボランチを務めていました。一方、代表チームではサイドバックやセンターバック、中盤で起用されることが多かったです。自分の感覚としては、試合で使ってもらえるのであればポジションはどこでも構わないというスタンスでした。ポジションについてはそのような感じでした。
久保田)スタイルについてはいかがでしたか?
加藤先生)その頃のディフェンススタイルはマンツーマンが主体でした。一対一で負けないことを最重要視し、一番気を使っていたのがポジショニングです。相手の意図を読む、ボールを受ける側の意図を読む、それを考慮して自分のポジションを取ることを常に意識していました。おそらく相手から見たら、結構しつこいディフェンスだったと思います。基本に忠実にプレーしていた、という感覚があります。
久保田)加藤久先生といいますと、ヘディングの強さが特長的でしたが、その秘密はありますか?
加藤先生)実は自宅にペンデルボールというものがあったのです。
久保田)東伏見のグラウンドにはありましたよね?あれがご自宅にもあったのですか?
加藤先生)はい。小学生の時に近くの鉄工所のおじさんに頼んだら、作ってくれたのです。「頼んだらいいよ」と言われて。それを使って、自宅の庭でジャンプヘッドやボレーの練習をしていました。ペンデル用の輪っかがついたボールを買ってきて、紐を付けて使っていました。ジャンプして空中で待ち、うまくインパクトしないと綺麗に戻ってこない仕組みなので、タイミングや精度を練習するのに最適でした。
久保田)空中で静止するような先生のジャンプヘッドのスタイルは、ご自宅での練習の賜物だったのですね。
加藤先生)そうですね。ジャンプのタイミングや空中で待って叩く感覚は、ペンデルボールのおかげです。身長は175cmでしたが、ヘディングで負けることはほとんどありませんでした。
久保田)たくさんの試合をされていろいろな歴史に残るところもあったと思うのですが、ご自身の中で印象に残っている試合はどのようなものがありますでしょうか?
加藤先生)年代ごとに色々とありますが、高校生までは「本当のサッカー」という感じではありませんでした。トップレベルを意識したサッカーに出会ったのは、大学に入ってからです。フィジカル的にも技術的にも、大学の関東大学リーグで鍛えられました。ただし、試合そのものは多くありませんでした。総理大臣杯、大学選手権、リーグ戦などをやっていく中で成長させてもらったという実感があります。
試合そのもので言えば、印象深かったのは大学4年生の時にいわゆるインカレ(全日本大学サッカー選手権大会)で優勝した時のことです。その時、タイムアップのホイッスルが鳴って優勝直後に堀江先生のところへ皆で行き、先生を胴上げしようとしたのですが、先生が「ちょっと待て」と言いました。そして、「君たちは1対0になってからずっと受け身に回っていた。次の点を奪いに行くということをしなかった。そういう受け身の人生を歩むのか?」と厳しく指摘されました。
久保田)優勝を決めた直後にそんなことを言われたんですか!(笑)
加藤先生)堀江先生の自伝『わが青春のサッカー』にも「嬉しくない優勝」という項目がありますが、その時のことが書かれています。優勝したにも関わらず、先生の前で私はもちろん、岡田や原もみんなうなだれていました。でも最後に先生は、「胴上げしたかったら、しろ」と言ってくれました。
当時はなぜ先生が怒るのか分かりませんでした。自分たちとしては必死に戦っていたので。しかし後になって分かったのは、先生が大切にしていたのは「結果」よりも「プロセス」だったということです。先生は常々、「プロセスは常に前向きでなければならない。積極的でなければならない」とおっしゃっていました。それが試合の中で我々には表現できていなかった、ということだったのだろうと思います。
勝って万々歳ではなく、勝ってもそうやって叱ってくれる人はなかなかいません。そのことは今でもありがたく思っています。その時、堀江先生に関わった私たちは、先生の深い敬愛に触れることができました。
そういう意味では、大学のインカレの決勝戦が一番印象に残っています。
あとは社会人になってから読売クラブに入り、そして、1985年のメキシコワールドカップ予選で、日本は韓国と戦った試合です。その頃はアジアのワールドカップ出場枠が2つしかありませんでした。現在は8.5枠ありますよね。
久保田)そこは大きな違いですね。今でも国の数は一緒ですよね。
加藤先生)当時アジアは西地区と東地区に分かれていて、それぞれの地区で1枠を争っていました。単純に比較はできないけれども、決定戦まで進めば韓国と対戦することになる仕組みでした。
西地区と代表決定戦にでた4チームは今の規定でいえばワールドカップに出れたのですが。
久保田)あのときはそんなに少なかったんですね(驚き)!
日本は1993年にJリーグが発足しましたが、韓国はそれより早い1983年にプロ化しており、やっぱり韓国は強かったですよ。日本は国立競技場で1-2で敗れ、アウェイでも0-1で敗北しました。韓国は出るにふさわしかったなと正直思いました。
当時の韓国の選手たちは素晴らしい選手ばかりでした。本大会ではアルゼンチンのマラドーナと対戦したのを見てましたが、韓国はその試合に敗れはましたが、もし日本が出場していたら同じような試合はできなかったのではないかと正直思います。韓国はアルゼンチン相手に善戦しましたが、力の差を感じさせられた試合でした。それでも、あの時の韓国の選手たちは素晴らしい戦いを見せていました。
久保田)プロになってJリーグではいかがでしたか?
加藤先生)実は、30歳くらいのときに一度引退をしようと思い、1990年のイタリアワールドカップでNHKの解説を頼まれて一ヶ月間、それを担当しました。約1ヶ月半もの間イタリアに滞在していたのですが、現役を引退したからこそ解説を引き受けたんです。そうしたら、当時、読売クラブの監督にカルロス・アルベルト・シルバという方が就任しました。その人はソウルオリンピックのブラジル代表の監督でした。その彼と、偶然ローマで出会ったんです。そして「あなたは加藤選手ですね?一緒にやりましょう」と言われました。それで一度は引退を考えていたのですが、1993年にJリーグ(プロリーグ)が始まります。「役員だとか指導者の立場で自分がJリーグを体験することは可能だろうけれども、辞めてしまったら選手としてその舞台を実感することはできないだろう」と思い直し、再び体を鍛え直して復帰することに決めました。
最終的には1994年に38歳で引退しました。マリノスとの開幕戦にも出場させてもらいましたが、その試合が始まるまでの盛り上がりは本当にすごいものでした。
自分としては、選手として「プロになった瞬間、何が違うのだろう」と考えていたのですが、開幕のキックオフの笛がピーと鳴った瞬間、「何も変わらないな」と感じたのを覚えています。要するに、ひとりの選手としてやることは何も変わらない。劇的に変わったのは、周りのメディアの扱いや社会の注目でした。
ただ、自分とサッカーとの関係は何も変わりませんでした。プロとアマチュアには確かに区別はありますが、アマチュアの中にもプロにふさわしい人はいますし、プロの中にもアマチュア的だと感じる人もいるな、それが自分の率直な思いです。
どのような舞台であれ、私はいつも真剣に試合に臨みました。プロもアマチュアも、本質的には何も変わらない。それが私の正直なところでした。
久保田)なるほど、そういったものなのですね。
加藤先生)当時は実は日本サッカー協会の仕事をしながら、選手としての活動を行い、大学にも勤務していて、「三足の草鞋」でした。これを1985年頃からずっと続けていましたが、正直、とても疲れていてよく血尿が出ていました。今振り返れば、よくこの三つの仕事をやり切ったと思います。
さらに、大学では教職員組合の仕事も順番で回ってきてしまい、最後の晩年には組合の執行委員も務めました。その会議が夜にあって、寝たら朝になっている、朝になるとかえって前の日よりも疲労が残っているという毎日でした。
これら三つの場で関わり続けることが、自分に与えられた役割だと思い、精一杯やりました。本当に、よく体と精神が持ったなと自分でも思います。
1993年には清水に行って、その際は東京から清水に通っていたのですが、そのときも血尿が出てしまい、自分でも驚きました。「体を少し休めたほうがいい」と言われましたが、すぐに復帰しました。限界まで頑張っていたのだと思います。
久保田) (東京ヴェルディのユニホームを着てラモス瑠偉さんと優勝カップを掲げている写真を加藤さんに見せながら)この間写真を見ていたらこういうのがあったのですが、この写真はどういう時の写真か覚えてらっしゃいますか?
加藤先生)これは1994年にヴェルディに戻ってJリーグチャンピオンシップでサンフレッチェ広島に勝ったときのものですね。この試合のときにはもう引退を決めていました。「負けて引退するのか、勝って引退するのか」といった感じでした。これはその時の表彰式の写真です。
久保田)ラモスさんが伝説のループシュートを決めた試合ですね。
加藤先生)1993年に、ヴェルディから清水に移籍したのですが、移籍することでいろいろ叩かれました。当時、日本で移籍するということはあまり考えられないものでした。ヴェルディでは当時の監督が他の選手を使いたいという意向があることが分かったので、自分としては必要とされる場所でプレーするために移籍を決断しました。ただ、そのときは本当にたくさん批判されました。
久保田)確か、日本プロサッカーリーグでの移籍第1号でしたよね。
加藤先生)そうです。今でこそ移籍は普通のことですが、当時は拍手喝采してくれる人もいれば、激しく叩く人もいました。スポーツ紙の一面になり、駅ビルの新聞スタンドを見ると、自分の名前が横になった短冊記事の見出しに載っていました。新幹線で帰ってきて電車に乗ると、中吊り広告にも自分の名前が出ていて、それも好ましい記事ではありませんでした。夕刊紙などで、人格がボロボロになるような記事がたくさん書かれました。
当時、妻にはそういった記事を見せないようにしていたのですが、妻の友達が「あなたのご主人がこんなふうに記事に出ているよ」とファックスで送ってきたりしました。「余計なことをするな」と思いましたね。本当のことで批判されるのは仕方ないですが、根拠のないことで叩かれるのは納得がいきませんでした。しかし、一つひとつ反論することもできず、理不尽な経験をたくさんしました。ただ、そのおかげで打たれ強くはなったと思います(笑)。家族がよく我慢してくれたなと思っています。客観的にみたら家族は私以上に被害者だったなと。
久保田)長い現役生活を経て、いろいろな地域や全国各地で活動されていたと思いますが、現役時代から現在まで、体に関してどのようなことに気を付けていらっしゃいますか?
加藤先生)現役時代は、「しっかり食べないと体がもたない」という感覚がありました。そのため、しっかり食べることを意識していました。それもバランスを考えてしっかり食べることを心掛けていました。どちらかというと「栄養が足りていない」というよりは、むしろ「過剰なくらい」を意識して食べていたと思います。
人間の調子は、体に取り入れるもので決まると考えています。一つは空気です。呼吸の仕方が大事だということには以前から気付いていました。いい空気を吸うこと、そして呼吸法、つまり吸い方や吐き方をしっかり研究していました。呼吸は精神状態にも影響するので、非常に重要だと思います。
もう一つは水です。私は水道水を飲むことはありませんでした。20歳ぐらいの時に海外に行ったら、みんなミネラルウォーターを飲んでいたのを見て、自分もその習慣を取り入れるようになりました。当時はガス入りやガス抜きのミネラルウォーターを飲み分けていました。学生時代から水道水を飲むことがほとんどありませんでした。その頃から水は買って飲むようにしていました。
久保田)当時はこういった習慣を持つ人は少なかったですよね。
加藤先生)私が現役だった頃は、練習中に「水を飲むな」という時代でした。みんなこっそり手を洗うふりをして水道水を飲んだりしていました。
久保田)そうですよね。私もバケツの水を飲んだりしていました(笑)
加藤先生)きちんと飲むときは、売っている水を飲んでいました。やはり体の状態は「食べ物」と「水」で決まると考えています。そして、精神状態は「空気」と「呼吸」で決まるという感覚がありました。そのため、それらは特に気を付けていました。呼吸法の研究も熱心に行っていました。
そうなると、メンタルトレーニングも取り入れることになります。たとえば呼吸法、いわゆるブリージングですね。例えばヨガや、日本独自の「気」を活かした方法などです。私自身、西野流呼吸法の西野皓三さんの教室に通ったり、合気道の道場に通ったりしていました。中にはプロのスポーツ選手も通っていました。そういったことを学び続けていて、今も学びを深めています。
現役を引退してからは、運動量が現役時代の十分の一ほどに減りましたが、筋力を落とさないようにトレーニングを続けています。現役時代から取り組んでいたので、少し筋力が落ちたと感じても、また始めればすぐに戻ります。筋肉は「記憶」しているようなもので、一度できるようになったことは、再び短期間で取り戻せます。たとえば、最初からベンチプレスで90キロを上げるのは大変ですが、一度そのレベルに達していれば、再び追いつくのは容易です。この「筋肉の学習能力」を実感しています。
ウェイトトレーニングについては、身長が175センチほどしかないから筋力トレーニングは非常に大切で、特にディフェンダーのように相手に合わせて戦うポジションでは重要です。私は現役時代から筋力を重視していました。大学卒業後の2年間は筑波大学に通い、1年目はどのクラブにも所属していませんでした。その間、筑波大学のサッカー部で試合に出るわけではありませんでしたが、ウェイトトレーニングを相当行いました。
昼休みには必ず筋トレをしていました。ダンベルを使ったり、腹筋台で腹筋をしたりしていました。スクワット、ベンチプレス、腹筋、背筋など、基本的な種目を重点的に行いました。その結果、タフな体を作り上げることができました。ただし、ライフスタイルとしては疲労を取る時間が少なく、やることが3つ重なっていたこともあり常に忙しい生活を送っていました。もう少し休養が取れていればよかったかなとも思います。。
まあ、やれることはやり尽くしました。たまたま大学で栄養や体づくり、心身のコントロールといった分野に触れる機会が多くあり、他の人よりもそういった知見に触れる機会はずっと多かったと思います。自分自身でも体験を重ねながら、呼吸法や体の調整などを学んできました。
久保田)いろいろ学生時代のことを思い出しますね。サッカー部に先生が指導にきていただいた時に呼吸のことをよく言われました。特に、呼吸の吸い方や吐き方についても、非常に重視されていたことを思い出します。
加藤先生)結局のところ、吸い込むものや体に取り入れるものが悪ければ、例えば毒ガスを吸えば命を落としますし、毒キノコを食べても同様に死に至ります。自分の身体に何を取り入れているのかを常に吟味することが大切です。思考もまた、自分の身体に取り入れるものだという意識を持った方がいいでしょう。要するに、悪いものを体に入れたらどんどん悪い現象が起こる、体に何を入れるかがすごく大事。
久保田)なるほど。
加藤先生)ただし、それを自分で矯正できる部分と気づけない部分があるので、そのために久保田先生がいる。
久保田)ありがとうございます。
加藤先生)いや、でも本当に気づかなくなることあるのですよ。
自分でも骨盤や背骨の歪みの状態はなんとなく意識していますが、肋骨の歪みとかの感覚はこれまで全く気づいていなかった。おそらくアスリートであれば背骨が曲がっているとか骨盤が歪んでいるといったことを意識する人もいるかもしれないけど、一般のひとは気づかずに病気とかをしている人多いのじゃないかなと思います。運動をしている人はそういう部分が敏感だから、気づけるかもしれませんが、一般の人はまったく気づかないまま日常生活の姿勢や習慣による歪みがどんどん進んでしまうこともあると思う。そういった問題をアドバイスしてくれる人が近くに縁があっているかいないかはすごく大事だと感じます。
久保田)ありがとうございます。
加藤先生)そういうことは、身をもって経験しないと人にも言えないから。
肋骨の歪みは、本当に盲点だった。今では、自分で少しずつ修正できるようになってきて。これは一回やればOKじゃなくて、常に調整をしないとダメなんですよね。それはすごく思います。これ(疲労が吹っ飛ぶ!10秒ゆがみリカバリー)は本当にすごい本だと思います。
だから、一般の人はわからないですよね。どうしても対処療法というか、部分最適のような発想になりがちだからね。私はどちらかというと、鍼灸や、もっと全体を見て考えるタイプなのですが。部分だけやるのではなくて。「全体が生きているのだから、もっと全体を見るべきでは?」と思ってしまう。
久保田)今回、改めてご連絡をいただいたきっかけ、うちの接骨院に来ていただけたきっかけはどういったところだったのでしょうか?この本(疲労が吹っ飛ぶ!10秒ゆがみリカバリー)はどこかでご覧になったのですか?
加藤先生)いやいや、知りませんでした。
ちょっと、いろいろやってみても体が戻らないな、と思うことがあったのでちょっと行ってみようとひらめいたのです(笑)
久保田)実際に院に来られた時の院内の雰囲気やスタッフの対応などはいかがでしたか?
加藤先生)「いいんじゃないかな」と思いました。正直、たくさんのスタッフを採用するということは、それぞれ動機とかキャリアが全然違うから、そういった人たちを生き生きと仕事に取り組ませるのは大変だろうなと思っています。
今、沖縄の子どもたちをボランティアでずっと見ていて、そこでスタッフを雇って運営しているのですが、やっぱり受け止め方や考え方の違いがあって、例えばこちらがこう伝えたから分かってくれるだろうと思っていても、全く違う受け止め方をされたり、そもそも言葉の意味を理解していなかったりすることが結構あります。意味というより、こちらの思いを理解していなかったりする場合もあります。
常に対面で接しているわけではないですから、現地にいる人たちに任せていますけれど、彼らには彼らの流儀があって仲間同士のやり方があるから、そちらの影響を受けてしまうこともあります。組織として、自分が責任者であり「我々はこういう理念や哲学を持っています」と説明して分かってもらえていると思っていても、実際には彼らなりのやり方で動いてくれるので、なかなか難しい部分があります。
対面で関わっていてもいろいろな思いがあるし、現場を運営する立場は本当に大変だろうなと思いながら見ています。
久保田)ありがとうございます。
加藤先生)それを人には言えないだろうし、愚痴を聞いてくれる人も責任者の立場になるといなくなりがちですから、大変だと思います。三店舗を運営していて、財務なども含めた管理の仕事などもあるでしょう。沖縄の役員の人も手伝ってくれていますが、経理の部分で「おかしいな」と思うことがあれば指摘して対応しなければなりません。
そのため、経営側に立つと気持ちがそちらに引っ張られる時間がものすごく多くなります。経営の立場は本当に大変だと思いますし、それでもよくやっているなと感心します。多分、当たっていると思いますよ。
久保田)ありがとうございます、おっしゃる通りだと思います笑。さすが先生です。
加藤先生)やっぱり、いい人材がある程度自分でできるようになってくると、独立しようとか、自分はちょっと違う考えを持っているとか、そういう気持ちが出てくるんじゃないかなと思います。そういうのが大変でしょうね。でも、経営ってそういうものだと思います。どんな会社でも「ここまできたらピシッとうまくいく」なんてことはないでしょうし、そういう現実を受け止めながらやらなくてはいけませんよね。一見、うらやましいというような事を言われても、実際のところ中身は大変なのだということをわかってもらう必要がありますよね。沖縄に行くと、子どもたちが生き生きとしているかどうかが一つのバロメーターでありますし、患者様もそうだと思いますが、子どもたちが明るく振る舞っている姿、それが論より証拠だと思います。その間に立っているのがトレーナーや、こちらで言えば指導者やコーチです。どういう振る舞いをしているか、最後に来てくれる子どもたちや患者さん、その反応を見るとだいたいわかるものです。そこを私は一番重要視しています。
そういう意味では、患者様やお母さんたちにもうまく声を掛けているのかなと思います。やっぱり、みんな不安を抱えて来ていますから。また、サッカークラブの仕事をしていると、「なんでうちの子を試合に使わないのか」と言われることもあるけど、それを決めるのは親ではなくコーチでしょう、と。そういった部分では、医療やトレーニングでも共通するところがあるのかなと思います。
経営って本当に大変ですから。なにも考えずに施術していればいいというものではないと思います。うまくいくときもあれば、コロナのように大変な時期もありますよね。コロナの時は本当に大変だったですね。だって接触できないですから。そうすると月謝も入らなくなるし、それ以外の協力してもらっていた人たちにも活動出来ないことでフィードバックができないですし、本当にあの3年間は大変だったですね。その間、保護者との連携や交流も途絶えてしまい、「感じる」ということがなくなっちゃったのです。世の中の人みんな、そういう経験をしたのではないでしょうか。
そしたら今度はSNSのようなものが出てきて、「言ったもん勝ち」「書いたもん勝ち」みたいな状況になりますよね。逆にそれをうまく使いこなさないと、自分がやっていることをうまく表現できない時代になっています。中間層がいなくて、「こっちかこっちか」みたいな世の中になってきていますよね。SNSだとグレーゾーンのような部分がなくて、「こっちかこっち」という極端な選択肢しかないように感じます。
久保田)確かにそうかもしれませんね。
加藤先生)「書いたもん勝ち」ってところもありますよね。昔だったら、みんなの中で誰かが「いじめたらダメだろう」といさめる存在がいましたが、今は自分の欲求を満たすために、嘘のようなことを書いても、それが本当のように見えてしまうことがあります。そういう意味では、SNSに対応するためにいろいろな神経を使わないといけなくなるし、対策も必要でしょうね。
例えば、治療を受けた方が「あそこに行ったらこんな感じになった」と勝手に書き込む人も出てくるかもしれませんし。自分に都合の良いようにしか書かないこともあるので、大変だと思いますよ。
今は店舗が相模大野と東林間、それから大和市の鶴間にありますよね。一緒にゴルフに行った84歳のおじいさんがいるのですが、その方に「久保田さんのところに行ったらどうですか」と紹介しています。その時、「相模大野にありますかね」とおっしゃっていたので、もしかしたら来るかもしれません。一応、名刺をお渡ししておいきました。その84歳の人はいまだにラウンドを自分で歩いてやっていのんですよ。
久保田)先生は当院に治療をしに当院に来ていただいて、施術を受けてどのような変化がありましたか?
背中が痛くて、内臓からきているのかなと思っていましたが、それが消失しました。完全にではないですが、だいぶ痛みが減りました。
あとは、右足のアキレス腱の手術の影響もあって、膝の裏側の腱とか、そういうところにしこりがまだ残っていますがかなり消失して、変な違和感などはなくなりました。矯正すると日常的に出ないですし。あとは肩甲骨のところにいつも吊ったような感じがあったのですが、それも消えてきました。劇的に改善しています。自分でも結構セルフケアをしています。
久保田)ありがとうございます。
加藤先生)これ(疲労が吹っ飛ぶ!10秒ゆがみリカバリー)をみんな買って勉強しろと言いたいです(笑)
久保田)ありがとうございます。改めて、体のケアや予防の大切さを感じた経験は今までにもありましたか?
加藤先生)そもそも体が動かなくなったら何もできなくなるから、ケアをするというよりも、現役中は最高のパフォーマンスを発揮しなければいけないという意識で取り組んできました。どの食べ物が良いのか、どんなトレーニングが最適なのか、そういったことを常に研究し、最高の方法を実践してきたつもりです。ですが、自分の努力や意志、あるいは限られた時間だけでは改善できない部分もあって、そこはやっぱり体のケアをしてくれる人の存在が必要不可欠でした。私が現役の頃は、妻木さんが代表チームに同行していて、合宿中に体調を整えてもらったことが多かった。代表合宿ではしっかりと回復させてもらえました。
私は自分の体を触ってもらうと反応が早く、元に戻るスピードが速い傾向がありました。たとえば、凝った筋肉でも意外と早く柔らかくなるといった感じです。
今は少なくとも月に2回はケアを受けるようにしています。また、月に1回は体の状態を確認してもらい、アドバイスを受けている。それを日常的に活かし適切なケアを続けることを意識しています。
別に長生きしようとは思っていませんが、最後まで自分の力で生活したい、心の中ではそう思っています。
久保田)今のスポーツをしている子供たちやアスリートに向けて、ケアの重要性やアドバイスをいただいてもよろしいでしょうか。
加藤先生)まず、楽しく生きがいを持ちながら自分の望むことを達成するためには、セルフケアやセルフコントロールがすごく大事で、ただし、「何をセルフケアすれば良いのか」「何に気をつけるべきなのか」ということは、意外と分かっているようでわかっていない。それを学ぶ必要があると思います。
私の場合、周りに栄養学の先生や、ウェイトトレーニングの第一人者のような方がおられました。その方からは、「ウェイトトレーニングをしたらスピードが落ちる」というのは迷信にすぎないと教わった。本当にその通り。体が重くなるのは一時的なものであって、筋力を上げることで瞬発力とスピードが掛け合わさり、むしろスピードが向上すると。そういったことを教えてくれる人が私の周りにいました。でも普通の人にとっては、そういった出会いはなかなかないかもしれません。それでも、自分でアンテナを張って学ぶ必要がある。
「縁がない」と言ってしまったら、何事も始まりません。自分で探しに行くことが大切だとおもいます。そして、何のために探すのかといえば、それは楽しく生きがいを持って活動するためです。小さなことの積み重ねが、大きな成果につながります。今はインターネットで検索すれば、「この原因がこうだ」といった情報が簡単に出てきます。でもそれは言葉だけの理解でしかないですから、それを皮膚感覚、つまり体感として理解することまで深めたほうがいいかと思います。
原理として、正しくトレーニングしないと正しくない習慣が身についてしまう。だからこそ「正しいもの」とは何かということを常に考える。それは一人ひとり異なるかもしれませんが、その根っこには原理原則というものが存在します。それを学べる「師匠」という存在が重要です。
久保田)最後に誠に恐縮ですが、うちの接骨院をどのような方におすすめしたいか、また、接骨院のスタッフに対するメッセージや期待していることについて教えていただけますでしょうか。
加藤先生)治療をする場所はそこら中に山ほどありますが、久保田先生は本物ですから。本物と会って、本物の意見をぜひ聞いてみてください、と私は声を大にして言いたいです。また、スタッフの皆さんは、くぼた先生を師匠と決めたなら、師匠が目指しているところをしっかり見てほしいと思います。師匠が残した結果だけを見るのではなく、師匠がどこを目指しているのかを理解してください。そこをトレーナーの皆さんにはぜひ伝えたいです。
久保田)今日は本当にありがとうございます。私自身も素晴らしい教えをいただきました。
加藤先生)いろいろ試行錯誤して、アンテナを張って努力されてきた結果だと思います。
久保田)くぼたスポーツ接骨院うちにいらっしゃる患者様も、レベルはそれぞれですけども、一生懸命スポーツで成功したいと思っています。それは代表クラスでも、地元の地域選抜クラスでも目の前のスポーツに真剣に取り組む姿勢は変わらないと感じますね。
加藤先生)プロの世界では「手っ取り早く稼ぎたい」「すぐに上手くなりたい」という考えを持つ方もいますが、はっきり言って、そんな方法はありません。正しいことを正しい習慣で、正しいやり方で続けなければ、結果は得られないのです。多くの方が「正しい」と思い込んで間違ったことを繰り返しているように感じます。その点を、私も改めて考えさせられました。
久保田)そうならないようにするためにはどうしたらいいと思いますか?
加藤先生)これはもう、その人の想いでしょうね。どうしても早く結果を得たいという気持ちが強い、一番はじめに話が戻りますが、たとえ優勝という結果が出ても、プロセスが良くなければ怒ってくれる人がいる。いま苦しんでいることが、実はもう少し先に進めば素晴らしい結果につながるんだと考えられる場合もあります。
苦労や困難を避けようとする感覚が強すぎるのは無駄だと思います。耐える力がなくなっていますから。今の時代、仕事が嫌だと思ったらすぐ転職してしまう。「ロイヤリティ」という言葉がありますが、それが薄れているのかもしれないですよね。
久保田)そうですね。
加藤先生)狡猾な人が得をしている、そういうものをなくしていかないといけないと感じます。
久保田)加藤先生、本日は長時間にわたり、貴重なお話をお聞かせいただき、誠にありがとうございました。先生のお話を伺う中で、私自身も学生時代に戻ったような気持ちになり、大変刺激を受けました。改めて、先生のご経験やお考えに触れることができ、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。