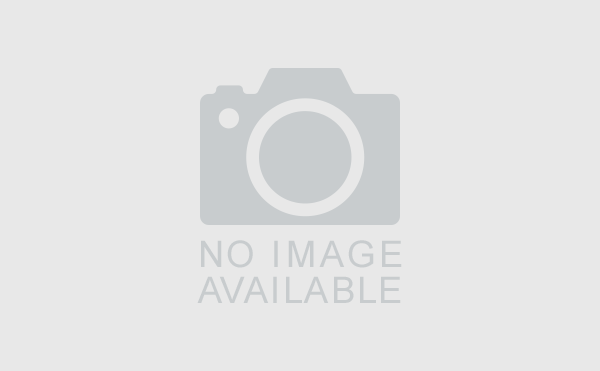肉離れの初期対応で大切なこと。
皆さんこんにちは。
今週のblogを担当します、スタッフの山口です。
今週のテーマは肉離れの初期対応で大切なことです。
コロナウイルスの影響で休止していた部活動やトレーニング施設が再開し少なくなっていた活動量も増えて来ている方も多いのではないでしょうか。
急激に活動量が増えると筋肉系のトラブルが起こるリスクも同時に高まります。
筋肉を痛めた時は初期対応が大切になります。痛めてしまった初日から自宅やスポーツ現場で出来るセルフ処置を中心に書いていきたいと思います。
今まさに怪我をしてしまった方やスポーツに関わる方なら知っておきたい知識です。少し長いですが是非お付き合いください。
≪肉離れの基礎知識は症例別の記事に詳しくありますこちらも合わせてご覧ください≫
≪自宅やスポーツ現場で出来るセルフ処置≫
・肉離れを起こすと筋肉の繊維が損傷され筋肉の周囲の血管も同時に傷つき皮膚の下で出血をおこします。初期の対応としてはこの出血を少なくすることが大切です。
・出血を少なくする方法について詳しくご紹介していきます。この方法をそれぞれの頭文字をとってRICE処置とも言います。

Ⅰ)安静(Rest):
肉離れを起こしたらまずは運動を中止しましょう。特にストレッチや痛めた筋肉を収縮すると強く痛みが出ます。このような動きにより筋肉の傷口が広がり血管の傷と出血量が増えてしまいます。歩いて痛いときはなるべく歩かないようにし、松葉杖をつくなどして痛みが出ないようにしましょう。
Ⅱ)アイシング(Icing):
損傷された組織に氷をあて冷やすことで周囲の血管を収縮させ出血を少なくすることができます。反対に湯船などに浸かり温めてしまうと出血は増えるので初期は控えましょう。
アイシングは通常氷のうを使い一回に15分~20分間行います。寝るときに冷湿布を貼るのも効果的です。※保冷剤を使うと凍傷を起こすことがあります。注意しましょう。
Ⅲ)圧迫(Compression):
自宅に伸縮性のある包帯やバンテージ、痛めた部位に適応したサポーター等がある場合は使用することをお薦めします。軽く圧迫することにより筋肉は動きにくくなり、出血量も少なくすることができます。
Ⅳ)挙上(Elevation):
長時間立っていると血液は重力により下(主に足)に溜まります。足を痛めた場合、寝るときや練習や試合を見学しているときに足の下に枕やタオルを入れて体よりも少し高くしてあげてください。溜まった血液を心臓に戻し出血を減らすことができます。
・セルフ処置で特に重要なのは1と2です。
なので…肉離れをおこしたら「安静にしてアイシング」と覚えておいてください。
・次に医療機関への受診をお薦めします。重症度に関わらず初期から適切な治療を行うことで痛みの緩和や予後(今後の状態)を良好に保つことができます。
痛みが少ない時でも肉離れの疑いがあるときは軽く見ず専門家の判断を仰ぎ治療をしていきましょう。
≪くぼたスポーツ接骨院での治療≫
・くぼたスポーツ接骨院では視診、触診、徒手検査により受傷部位と重症度の判断、それに応じた適切な治療を提供させていただきます。
①受傷初期の急性期
腫れを引かせ安静にすることが大切です。
アイシングと電気治療を組み合わせることにより腫れを引かせ、インディバという治療器を使い特殊な高周波により腫れを引かせるのと同時に組織の回復を促進させる治療を行います。
伸縮性のある包帯を筋肉の捻れをなくす方向に巻き圧迫固定します。痛みの強さに応じて松葉杖の貸し出しもしています。


②組織が回復してきた慢性期
・超音波治療やハイボルト治療等の物理療法と手技療法を中心におこないストレッチでの痛みをなくしていきます。
・その後筋力を正常に発揮できるようにして再発を予防する体幹トレーニングや筋力トレーニングなどのエクササイズ指導やテーピング、最終的に目標となる競技の復帰のためのリハビリメニューの提案を患者さんの症状や競技特性に合わせてさせていただきます。


・また当院では様々な医療機関と提携させていただいております。患者さんの症状によっては必要に応じて精密検査をしていただける病院へのご紹介も可能です。
〔〔 くぼた院長のワンポインアドバイス 〕〕
・アイシングの際の氷のうですが、当院でも使用しているアクティバイタルアイシングパックをお薦めします。
・氷のうと伸縮固定ベルトが一体化した構造で様々な箇所に固定ができ正しい位置を素早くアイシングしながら圧迫をすることができます。
・「氷」と「水」を混ぜて使用することにより凍傷対策にもなります。
・ビニール袋とは違い乾かして何度も繰り返し使えるのでコストの面でもお薦めしております。
・院の窓口でも販売しているのでお問い合わせください!!
最後までご覧になっていただきありがとうございました。皆様の役に立つ情報はありましたでしょうか。
当院ではインスタグラム、フェイスブック、YouTubeチャンネルなどで怪我やリハビリに関する情報をアップさせていただいておりますので是非ご覧になってください。